CHRONOLOGY
- 年表
日本インフォメーションの出来事
社会一般の出来事
1945 - 1974 / 昭和29~49年
創業に至るまで
詳しく見る
創業者加藤和親の起業の決意

出典:国土地理院ウェブサイト 地図・空中写真閲覧サービスより。トリミングして使用
社会一般の出来事
1974 / 昭和49年
日本インフォメーション株式会社(NIC)誕生
詳しく見る
日本インフォメーション株式会社のはじまり
社会一般の出来事
1976 / 昭和51年
NIC設立後、初めての社員旅行

社会一般の出来事
1979 / 昭和54年
本社移転(名古屋市千種区、住友生命千種ビル)
詳しく見る
本社を移転して拡張

社会一般の出来事
1981 / 昭和56年
第2回増資~資本金14.3百万円
社会一般の出来事
1982 / 昭和57年
大阪支店開設(大阪市東区横堀)
社会一般の出来事
1984 / 昭和59年
浜松営業所開設(浜松市田町)
社会一般の出来事
1984 - 1986 / 昭和59~61年
第3~5回増資~資本金35.1百万円
社会一般の出来事
1985 / 昭和60年
東京支店(当初は「東京SEセンター」)開設(東京都港区虎ノ門)
品質チェック子会社、株式会社シー・ティー・シー設立
社会一般の出来事
1987 / 昭和62年
大阪支店移転(大阪市淀川区、住友生命新大阪北ビル)

第6回増資~資本金37.9百万円
社会一般の出来事
1988 / 昭和63年
全国オンラインネットワーク完成
詳しく見る
3拠点を結ぶオンラインネットワーク
第7回増資~資本金40百万円
東京支店移転(世田谷区太子堂、住友生命三軒茶屋ビル)
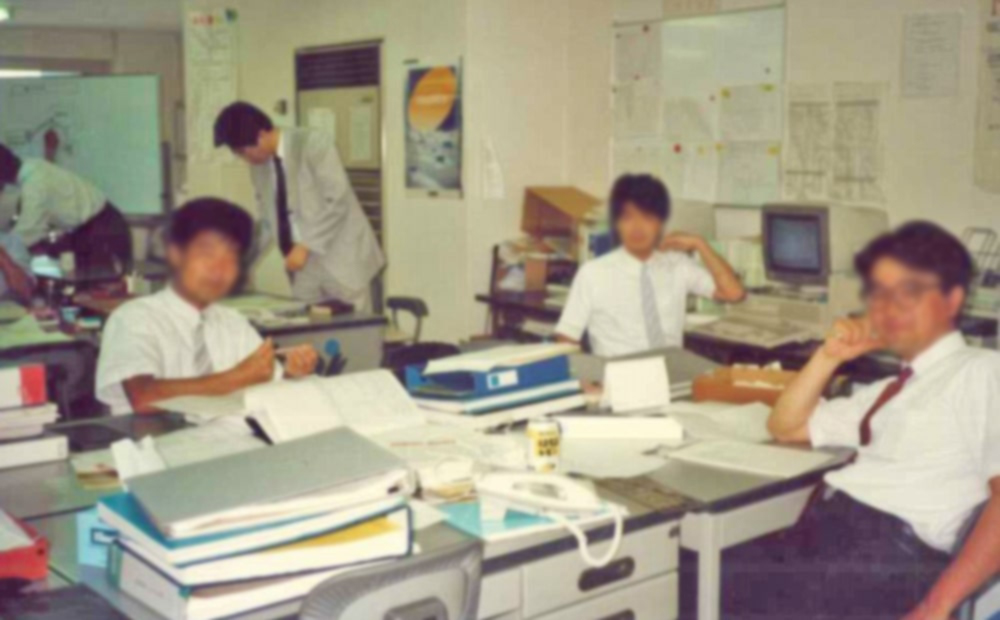
社会一般の出来事
第2章 動乱期
1989 - 1994
1989 / 平成元年
拠点ごとに子会社設立
詳しく見る
各拠点を子会社化
第8回増資~資本金60百万円
創業15周年
詳しく見る
創業15周年を記念してパーティを開催

自社ビル竣工(今池ソフトビル)
詳しく見る
今池に自社ビルを建てる

社会一般の出来事
1990/ 平成2年
社員持株会を発足し、従業員の持株を同持株会に集約
第9~10回増資~資本金1億95百700千円
東京支店移転(世田谷区太子堂、東京日産太子堂ビル)
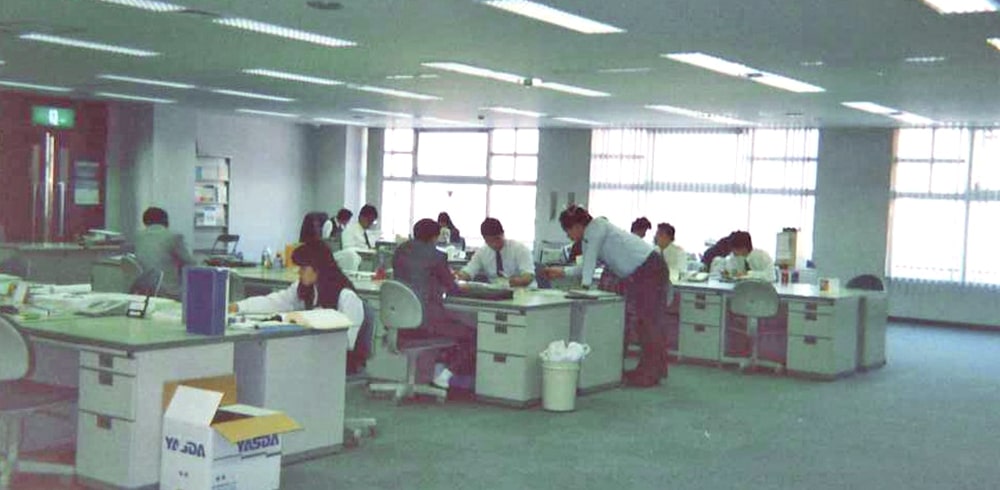
北大阪支店開設(大阪市淀川区、大阪北野第一生命ビル)

社会一般の出来事
1991/ 平成3年
浜松営業所の支店昇格
子会社6社の整理統合
詳しく見る
会社組織の再編成
第11回増資~資本金4億10百200千円
詳しく見る
第11回増資で現在の資本金額に
各種フェア・企業展に積極出店

初の赤字決算
詳しく見る
バブル崩壊の影響を受けて
社会一般の出来事
1992 / 平成4年
株式公開の先送り
詳しく見る
続く不況による方針転換
社会一般の出来事
1993 / 平成5年
本社移転・名古屋拠点集約
詳しく見る
名古屋市内の拠点をまとめる
社会一般の出来事
1993~1994 / 平成5~6年
東京支店移転・大阪拠点集約・浜松支店閉鎖
詳しく見る
各拠点の集約化
社会一般の出来事
1994 / 平成6年
売上高の大幅ダウンと赤字
詳しく見る
経営危機の真っただ中で
地域別子会社設立
詳しく見る
独立採算を狙い、子会社を設立
業績回復
詳しく見る
明るい兆し
社会一般の出来事
第3章 伸張期
1995 - 2002
1995 / 平成7年
Windows®95の登場で過去最高売上高更新
詳しく見る
画期的なOSの波に乗る
社会一般の出来事
1998 / 平成10年
豊田営業所開設
詳しく見る
取引拡大を狙った開設
地域別子会社の吸収合併
詳しく見る
地域別子会社の終焉
社会一般の出来事
1999 / 平成10年
売上高20億円達成
詳しく見る
需要増に乗って業績拡大
創業25周年
詳しく見る
危機を乗り越え迎えた25周年

社会一般の出来事
2001 / 平成13年
東京本部移転(中央区銀座、銀座クイント)
詳しく見る
業績安定に向けた拠点再編成

社会一般の出来事
2002 / 平成14年
大阪本部移転(中央区船場中央、堺筋本町センタービル)

社会一般の出来事
2003 / 平成15年
豊田営業所移転(豊田市、ギャザビル)

Microsoft solution lab開設(名古屋市中村区、太陽生命名駅ビルほか)

社会一般の出来事
第4章 飛躍期
2004 - 2013
2004 / 平成16年
創業30周年
詳しく見る
全社員で親睦を深めた周年行事

社会一般の出来事
2006 / 平成18年
ISO27001(ISMS)認証取得
詳しく見る
国際規格の認証を受けたサービスを
本社・名古屋本部移転
詳しく見る
人員増加に伴う移転

社会一般の出来事
2006 ~ 2007 / 平成18~19年
過去最高売上高計上
詳しく見る
好況な業界において売上高40億円突破
社会一般の出来事
2008 / 平成20年
盛岡オフィス開設
詳しく見る
市場開拓のための新拠点

基幹業務システムGRANDIT®導入
詳しく見る
株式公開のための取り組み

リーマン・ショック
詳しく見る
世界的不況との遭遇
社会一般の出来事
2009 - 2010 / 平成21~22年
リーマン・ショックによるリストラクチャリング
詳しく見る
大不況を乗り切るために
社会一般の出来事
2010 / 平成22年
日本で発売前の「iPad®」で新製品の開発に着手
詳しく見る
新製品の開発をスタート
いち早くiPad®を入手
詳しく見る
他社に先行した開発
電子プレゼンテーションシステム「Ebooklet2」開発
詳しく見る
ついに新製品が誕生
社会一般の出来事
2011 / 平成23年
東日本大震災の発生
詳しく見る
創立記念日に起きた巨大地震
ペーパーレス会議システム「スマートセッション」開発
詳しく見る
ロングセラー製品の誕生
岩手NIC株式会社を設立
詳しく見る
岩手・盛岡の復興の一助に
加藤高章の帰国
詳しく見る
新たなチャレンジ
NIC Global Solutions株式会社設立
詳しく見る
ITコンサルティング会社の立ち上げ
東京本部移転(東京都中央区京橋、京橋第一生命ビルディング)

社会一般の出来事
2012 / 平成24年
今池ソフトビル売却
詳しく見る
自社ビルとの別れ

社会一般の出来事
2013 / 平成25年
岩手NIC株式会社営業開始
詳しく見る
東北の新拠点のスタート
社会一般の出来事
第5章 発展期
2014- 2023
2014 / 平成26年
創業40周年
詳しく見る
40周年を記念して社史の発刊も

2015 / 平成27年
加藤高章が代表取締役に就任
詳しく見る
社長の交代
社会一般の出来事
2016 / 平成28年
子会社である岩手NIC株式会社を吸収合併
詳しく見る
収益力を高めるための決断
熊本地震の被災者への義援金1百万円を寄付
大阪本部移転
社会一般の出来事
2017 / 平成29年
ISMSの拡張認証であるISO27017 ISMSクラウドセキュリティ認証を取得
2018 / 平成30年
2017年度のスマートセッションの販売累計250社突破(255社)
奨学金返済支援制度を導入
詳しく見る
独自の支援制度の策定
社会一般の出来事
2019 / 平成31年・令和元年
2018年度のスマートセッションの販売累計300社突破(317社)
システム部門の事業部制導入
詳しく見る
新たな軸を設けて人的リソースを活用
中長期行動目標の策定
詳しく見る
会社の行動の方向性を明確化
ベトナムを海外進出候補地として決定
詳しく見る
海外進出を実現するために

社会一般の出来事
2020 / 令和2年
2019年度のスマートセッションの販売累計350社突破(389社)
「新規ビジネスの創出」に向けた体制強化
詳しく見る
体制強化とSatellite Labの開設
広報室の設置
研修制度「PM研修」「年次研修」を導入
詳しく見る
研修制度の見直し

社会一般の出来事
2021 / 令和3年
東京本部移転(東京都中央区新川、アステール茅場町)
「第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021」受賞
詳しく見る
スマートセッションが奨励賞に輝く
2020年度のスマートセッションの販売累計400社突破(423社)
社会一般の出来事
2022 / 令和4年
「第16回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022」でスマートセッションが「支援業務系ASP・SaaS部門 働き方改革賞」を受賞
名古屋市の外国人雇用支援事業の研修実施
詳しく見る
誰もが働きやすい職場を目指して

2021年度のスマートセッションの販売累計450社突破(456社)
社会一般の出来事
2023 / 令和5年
ベトナムホーチミン市に駐在員事務所を開設
詳しく見る
コロナ禍を超えて海外へ進出
ホワイト企業認定でゴールドを取得
詳しく見る
職場環境を整える一環として

2022年度のスマートセッションの販売累計500社突破(528社)
ベトナムのジョブフェアに参加
詳しく見る
現地の学生と直接交流

「第17回 ASPICクラウドアワード2023」でスマートセッションが「支援業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞」を受賞
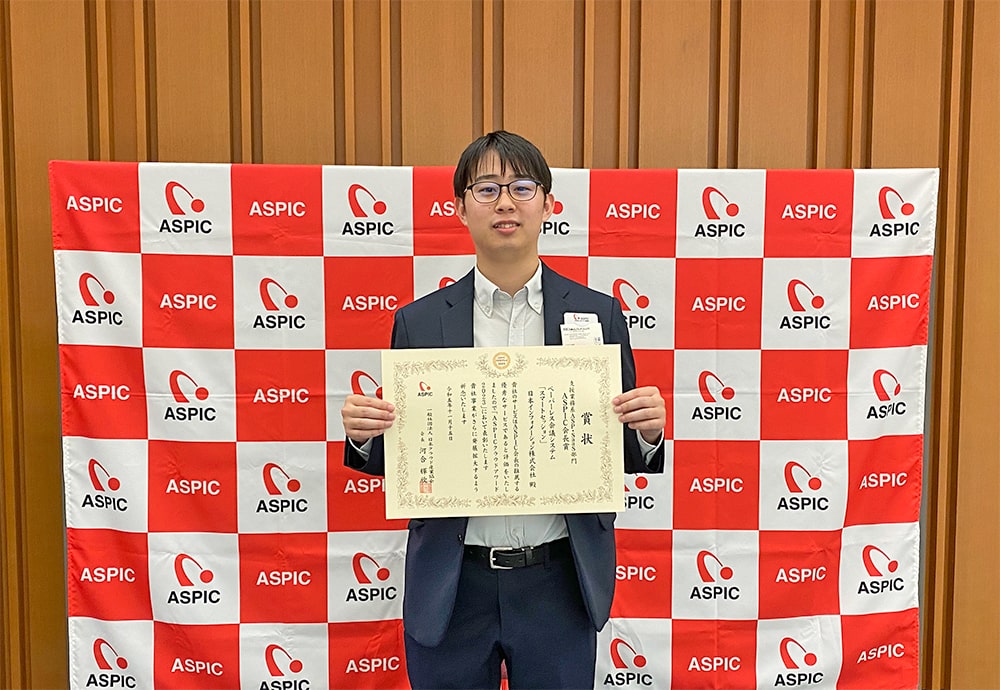
社会一般の出来事
2024 / 令和6年
能登半島地震の被災者への義援金1百万円を寄付
ベトナム現地法人の設立計画
詳しく見る
50周年を記念した計画
株式会社ホロニクスの株式取得
詳しく見る
シナジーの発揮と新規分野進出を狙って

ベトナムの現地法人NIC VIETNAM CO., LTDの設立
詳しく見る
初の海外現地法人の誕生

社会一般の出来事